リード(結論)
- 収入変動のたびに悩むのはムダな意思決定コスト。
- **あらかじめ「超過分の配分表」**を決め、AIに毎月の判定&提案をさせれば、感情に左右されず積立が増えます。
- 基本は新NISA×インデックス×ドルコスト。30年の視点で、**“止めない・迷わない・続ける”**だけ。
1. 生活防衛資金の確保(最優先ルール)
まずは生活防衛資金=生活費の6か月分(目安)を現金で確保。
- まだ足りないなら:超過分はまず現金へ(満たすまで)
- すでに満たしたなら:以降は**全て「投資側のルール」**へ回す
生活防衛が先、投資は後。ここを守ると暴落時でも積立を止めずに済みます。
2. “超過分”の配分表(例:昇給・ボーナス時)
家計が黒字化した**「超過分」**に対して、最初から配分率を固定します。
(※下はテンプレ例。ご家庭の事情に合わせて%は調整可)
2-1 月収UP時(ベースアップ)
| 用途 | 目安配分 | ねらい |
|---|---|---|
| つみたて増額(新NISA・インデックス) | 70% | 積立ベースを底上げ |
| 特定目標(教育/住宅など) | 20% | 目的別の別口座へ |
| ライフアップ(経験投資/自己投資) | 10% | 継続のモチベ維持 |
例:月収+10,000円 → 7,000円を毎月のつみたてに上乗せ。残りは目的別と自己投資に。
2-2 ボーナス増額時(一時金)
| 用途 | 目安配分 | ねらい |
|---|---|---|
| 追加一括投資(新NISA内のインデックス) | 50% | 将来の複利を増やす |
| 教育・住宅などの積立口座 | 30% | 目的の可視化 |
| 生活アップ/クッション(現金) | 20% | 防衛資金の補充・安心感 |
±5%リバランスの観点で、**“足りない側”**に一括投資の向きを寄せると、売却なしで整えやすい(年1回総点検の方針と整合)。
3. AIプロンプト(家計入力→即提案)
3-1 月収UPがあった月
あなたは家計×投資の“追加配分コーチ”です。
前提:生活防衛資金は6か月分確保。長期方針=新NISA×インデックス×毎月つみたて、30年運用。
今月の収入超過は【+10,000円】。現在の配分ルール=つみたて70% / 目標資金20% / 自己投資10%。
出力:
1) つみたて増額額(毎月の定額をいくら上げるか)
2) 足りない側(±5%コリドーで不足)のカテゴリを優先する“向き先”
3) 目標資金・自己投資の金額
4) 来月までのチェックリスト(3件)
注意:売却提案は不要。感情語を入れず、手順のみ。
3-2 ボーナス支給月
前提:ボーナスの超過分は、投資50% / 目標30% / 現金20%。
リバランス方針:±5%超は“新規資金で戻す”を優先(売却は最終手段)。
入力:現在の資産配分、目標配分、ボーナスの超過【+200,000円】。
出力:
1) 追加一括投資の金額と“向き先”(足りない側へ)
2) 目標資金・現金の配分額
3) 実行手順(NISAのつみたて増額 or 成長投資枠の活用はオプション)
4) 実行メモ(1行)
3-3 生活防衛資金が未達のとき
生活防衛資金が不足。投資は一時的に増やさず、超過分は全額“現金クッション”へ。
条件を満たしたら、自動で通常の追加配分に戻すルール案を提示してください。
出力:現金が6か月分に到達する見込み月、以降の通常配分への復帰手順。
4. 増額手順(実装チェックリスト)
- 配分表を決める(↑のテンプレを家計版に微調整)
- AIに月次タスクを登録(「超過分判定→金額→向き先→実行メモ」)
- 証券口座の“自動つみたて”金額を更新(開始日を翌月1日に)
- 一時金は“足りない側”に一括投入(NISA内での追加が最優先)
- ログを1行:日付/増額額/向き先(米国・国内・全世界 etc.)
- 翌月の給与日に再点検(AIにリマインド:増額の定着確認)
5. よくあるつまずき → 先回り対策
- “余剰が出たら考える”は先延ばし:配分表を先に決めると迷いが消える。
- 暴落で止める:生活防衛資金があれば止めないで済む。**AIに「止めない宣言」**を月次で再確認。
- 贅沢に全部回る:自己投資10%枠で満足感を確保、残り90%を資産形成へ。
- 売買で合わせに行く:±5%はゆらぎ枠。新規資金で方向づけが基本。
6. まとめ(仕組みで上げる)
- 超過分の配分表+AIの定例提案で、収入UPがそのまま積立UPに変わる。
- 30年の視点で、新NISA×インデックス×ドルコストを続けるのみ。
- 今日の増額が、未来の“安定資産”の差になります。
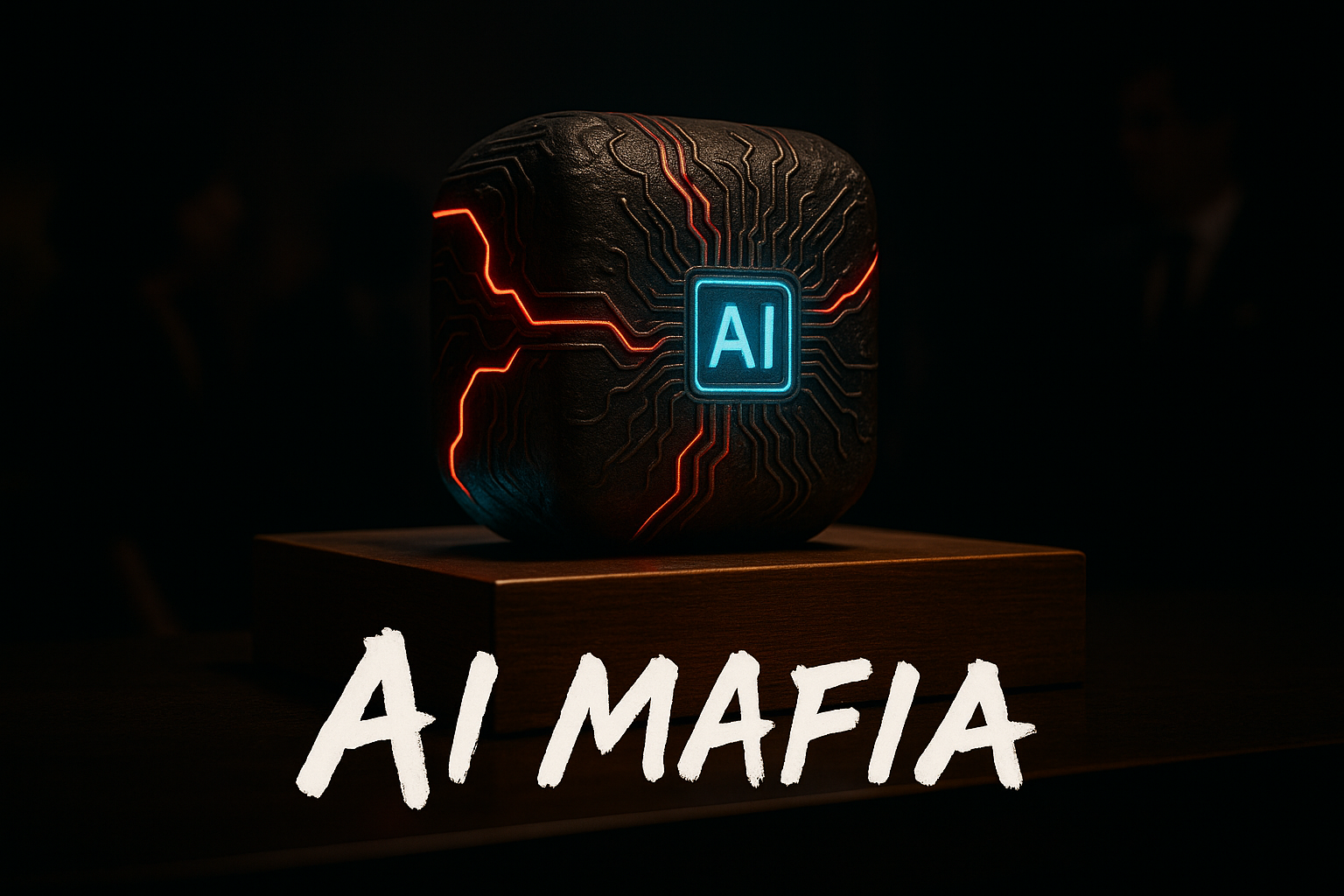

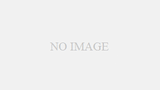
コメント