リード(結論)
- 長期投資で大事なのは、相場ではなく自分の“胃の強さ”。
- AIクイズで“下落に耐えられるか”を数値化 → 診断結果に合わせて配分を微調整。
- 目指すのは、“続けられる”配分+年1回の点検+月次の意思確認。
1. 許容度の測り方(3つの観点)
- 時間軸:目標は30年など長期か/途中で取り崩す必要があるか
- クッション:生活防衛資金は6か月分を現金で確保できているか
- 胃のテスト(Sleep Test):**-20%**の下落でも“積立を止めずに続ける”と決められるか
原則:配分は**“理想”より“継続できる現実”**で決める。少し保守的に始めて、慣れたら増やす方が失敗が少ない。
2. AIクイズ(Q&Aで3分診断|コピペOK)
プロンプト(そのまま貼る)
あなたは長期インデックス投資の“リスク許容度コーチ”です。
目的:下落20%でも“つみたてを止めない”配分を見つける。
質問(各0〜4点でスコアリング、合計20点満点):
Q1. 投資の目的と期限(10年未満/10–20/20–30/30年以上)
Q2. 生活防衛資金(0〜3か月/3〜6/6〜12/12か月以上)
Q3. 年収と家計余力(不安定/やや不安/安定/非常に安定)
Q4. 下落への心理反応(-10%で不安/-20%で不安/-30%でも継続/-40%でも継続)
Q5. 投資経験(初めて/1〜3年/3〜5年/5年以上)
出力:
1) 合計点とリスク帯(A:17–20、B:13–16、C:9–12、D:0–8)
2) “胃に優しい”基準配分の提案(例:A=全世界株100%、B=80/20、C=60/40、D=40/60)
3) -20%時の金額シミュレーション(評価額300万円なら△60万円 等)
4) 行動宣言(つみたて継続/売買回転しない/年1回点検)を1行
5) 来月の自己点検チェックリスト(3つ)
注意:特定銘柄の推奨は不要。インデックス“カテゴリ”で提案。
スコアの読み方(例)
- A(17–20点):下落に強い → **全世界株100%**から開始
- B(13–16点):やや強い → 株80%+債20%
- C(9–12点):標準 → 株60%+債40%
- D(0–8点):慎重 → 株40%+債60%(慣れたら段階的に株比率UP)
どの帯でも:新NISA×低コストインデックスで毎月自動つみたて/**年1回+5%**ルールで点検。
3. 配分の微調整指針(“続けるため”の下げ止まり)
3-1 胃が痛いと感じたら(保守側へ1段階)
- 例:株80/債20 → 株70/債30(10%単位で)
- 売却せず:今後の新規資金の向き先で徐々に調整
- 月3分:AIに「-20%時の金額」を再表示→感情を見直す
3-2 慣れてきたら(攻め側へ1段階)
- 例:株60/債40 → 株70/債30
- 3か月続けて平穏なら昇格、無理なら戻す——往復OK(続けるのが最優先)
3-3 乖離は“±5%コリドー”
- 年1回点検で**±5%超なら新規資金で戻す**
- 売却は最終手段(税コスト・心理負担を避ける)
4. AIテンプレ(診断→結果ページの作り方)
4-1 診断ページ生成(見出し+表)
目的:リスク許容度の診断結果ページを作る。
入力:総合スコア、推奨配分(株/債)、-20%時の金額、行動宣言。
出力:①見出し(あなたのリスク帯はB)②配分表(株/債、±10%の範囲)③-20%シミュレーション④行動宣言⑤次回点検日
4-2 月次チェック(5分で)
今月の“胃の調子”点検。Q1:先月より不安?同じ?Q2:積立は継続できた?Q3:生活防衛資金は6か月分維持?
出力:来月までの小タスク(3件)、必要なら配分を±10%で1段階だけ調整提案(新規資金の向き)。
5. NG行動リスト(壁に貼る用)
- 暴落で積立停止
- 短期ニュースで乗り換え
- 生活防衛資金を侵食
- 配分を毎月いじる(年1回で十分)
6. まとめ(“守れる約束”が最強)
- 診断→配分→行動宣言をAIで可視化。
- 微調整は±10%の階段、点検は年1回+±5%。
- 止めない・売らない・続けるが、30年後の差になる。
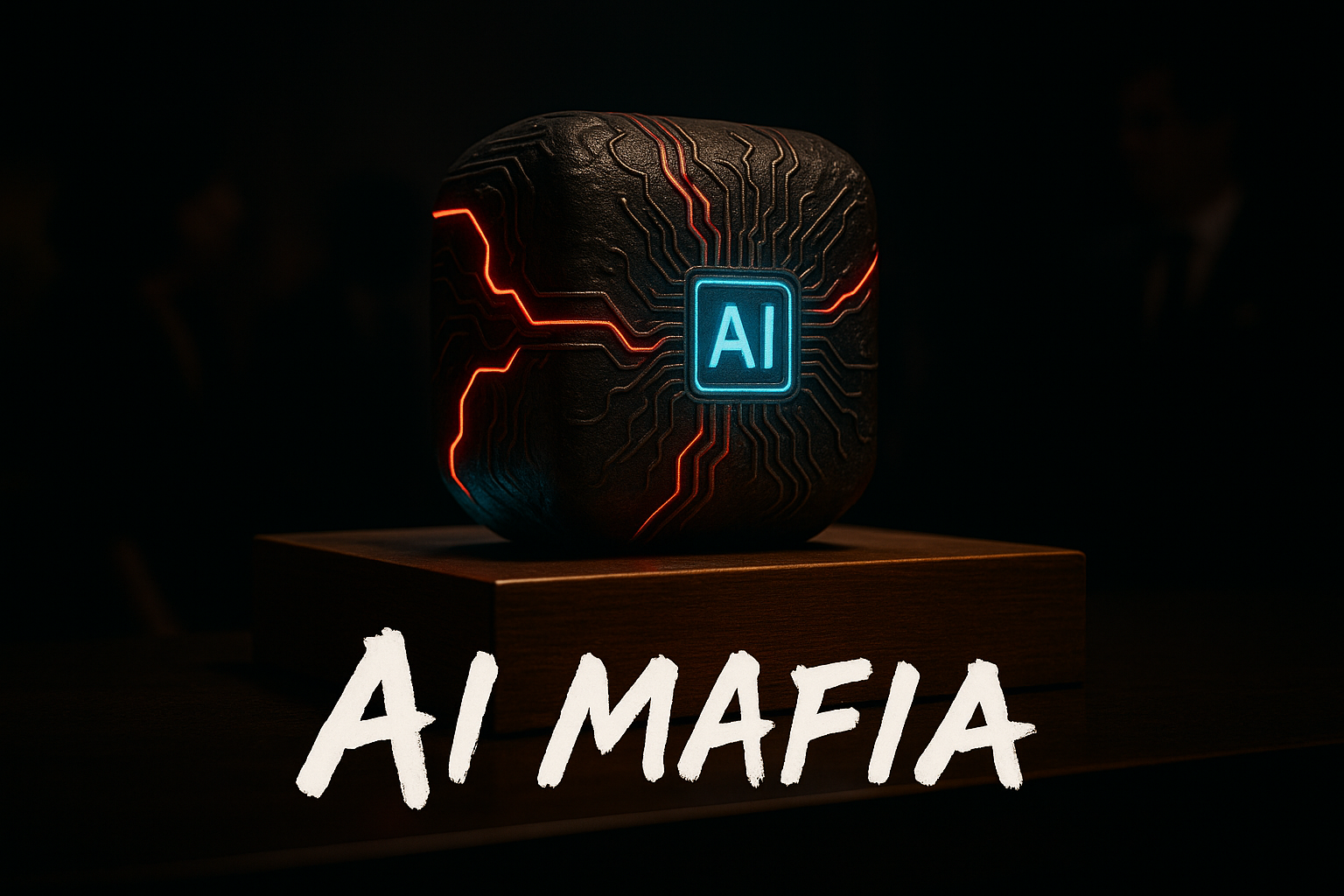

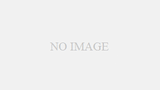
コメント