リード(結論)
- 長期投資の要は**「続けるためのルール」**。
- 年1回だけ総点検し、基準配分から±5%超の乖離があるときに最小の手数で戻す。
- 原則は新規資金で調整、売却は最終手段。判定・指示はAIの定型プロンプトに任せて、感情を排す。
1. 基準配分(まず“基準”を固定)
例:
- 株100%(全世界) … 迷ったらコレ。
- あるいは 株80%+債券20% … 価格変動をやや抑えたい人。
基準は年の初めに1回決める。月中でコロコロ変えない。
2. 乖離診断(±5%のコリドー方式)
- 判定タイミング:年1回(誕生月や年末など固定)
- 判定基準:カテゴリごとの**目標比率から±5%**を超えたら「要調整」
- 考え方:±5%以内は**“許容ゆらぎ”**=触らない。ムダな売買回転を避ける。
(サンプル)
- 基準:株80%/債20%
- 現在:株86%/債14% → +6% 乖離 ⇒ 要調整
3. 新規資金での調整を“最優先”
- 積立方向の微修正で戻す(足りない側へ向ける)
- 目標は**数か月〜1年で“±5%以内”**に自然復帰
- 売らない:税・コスト・心理負担を避けるため。NISA内でも、売買回転はミスの温床
(サンプル指示)
- 「株が+6%多い → 今後の買付は“債券”側に寄せる/増額は債券に回す」
4. やむを得ない売却の手順(最終手段)
下記のどれかに該当する場合のみ検討:
- 新規資金で戻す余地が当面ない
- リスク管理上、配分逸脱が大きい(±10%など)
- 商品入替・運用終了で実務的に必要
手順(最小限)
- ①売却は過大側のみ
- ②売却額は必要最小限
- ③次回以降の積立で細かく整える(再度の売買を避ける)
- ④実行ログを1行で残す(理由/金額/日付)
5. AIプロンプト集(コピペOK)
5-1 年1回の総点検(判定→指示出し)
あなたは長期インデックス運用の“年次点検係”です。
基準配分:〔例〕株80%/債20%(固定)。許容ゆらぎ:±5%。
入力:評価額と現在配分(株・債など)と、来年の年間積立額の見込み(例:60万円)。
出力:
1) 乖離率をカテゴリごとに算出→±5%超を「要調整」と表示
2) 「新規資金で戻す」前提の買付配分案(何ヶ月で±5%内に戻るか)
3) なお戻らない場合の最小限売却案(額・理由・注意点)
4) 来年の初期積立配分(足りない側へ寄せる)と、次回点検日
5-2 月次ミニ点検(回転を増やさない確認)
今月は積立を継続。乖離は年次点検まで原則放置。
出力:1) 積立額の増額余地(家計余剰) 2) 足りない側への“微修正”案 3) 行動メモ(3件)
注意:売却提案は不要。年次まで触れない。
6. 具体例(数値でイメージ)
- 基準:株80/債20
- 年次点検:株86/債14(+6%乖離)
- 指示:来年の積立を“債寄り”に設定(例:株60%/債40%で半年)→半年後に株82/債18 → 年内に株80/債20へ自然復帰
- 売却は実施せず(手数料・メンタル負担ゼロ)
7. 実行ログ(続けるための“1行”)
- 2025/01/10:年次点検。株+6%。債寄り積立に半年変更。売却なし。
- 2025/07/10:中間確認。株+2%。通常配分に戻す。
- 2026/01/10:年次点検。±3%。変更なし。
“やったこと”を1行で残すとブレにくい。次回の自分へのメモ。
8. よくあるQ&A
Q. ±5%は厳しすぎ?
A. 目安です。±10%でもOK。目的は回転を増やさず整えること。
Q. 途中で基準配分を変えていい?
A. 年1回だけ。月中にコロコロ変えないことが継続のコツ。
Q. 売却は本当に要らない?
A. 多くのケースで新規資金の向き先を変えるだけで戻せます。売却は最終手段に。
9. 年1回の点検テンプレ(DL案)
- 入力:評価額/現在配分/来年の積立額
- 自動:乖離率計算/±5%判定/新規資金で戻す配分案/必要なら最小売却案
- 出力:来年の初期積立配分/次回点検日/1行ログ欄
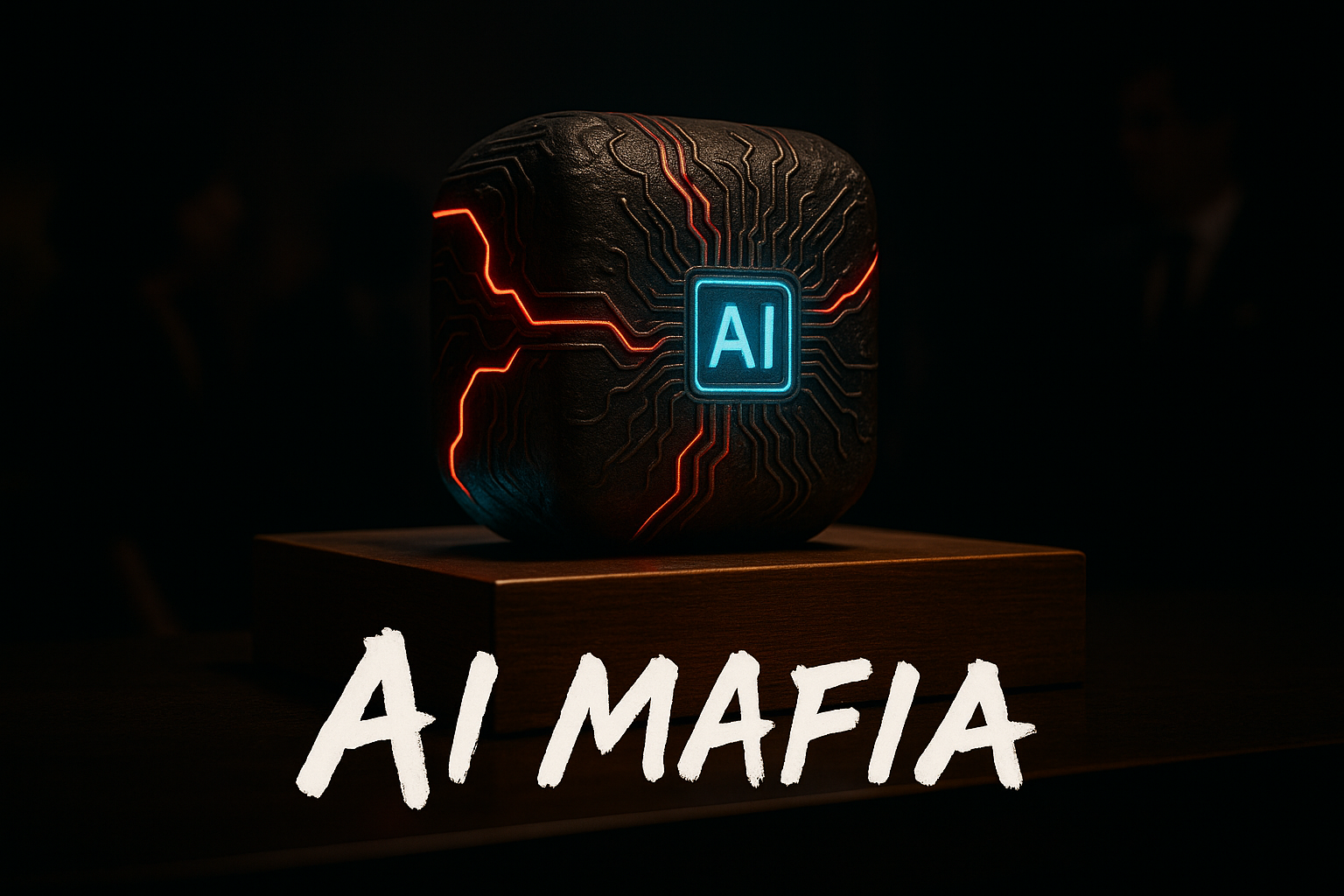

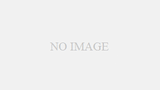
コメント