リード(結論)
- **基準は全世界株式100%**でOK。迷うなら「世界に丸ごと」で長期継続が最優先。
- ただし、米国や国内への“ゆらぎ”は小さく管理。±5%の範囲に収めると“直したくなる病”を防げます。
- AIに乖離検知と修正案の作成を任せると、感情を挟まずに運用できます(売却より新規資金の向き先で整えるのが基本)。
1. 基準配分(オールカントリー基準)
- 基準:全世界株式100%
- 目的:国・地域・通貨を跨いで広く分散/個別判断を最小化/**長期で“続く”**ことを最重視
- よくある“ゆらぎ”:
- 米国のニュースを多く目にして米国比率を上げ過ぎる
- 「地元を応援」で国内比率を増やし過ぎる
- ルール化:
- 米国・国内などサブ配分の“許容ゆらぎ”=±5%
- 例)「米国は基準(全世界内の比率)から**±5%以内なら放置。超えたら次回の新規買付を米国“以外”に回す**」
ポイント:“ゆらぎ”をゼロにしない。ゼロを目指すと取引が増え、コストや手間で続かなくなるため。
2. ±5%ルール(コリドー方式)
- 判定:
- 月1回、基準(全世界)に対する自分の実配分をメモ
- 米国比率・国内比率が基準から**±5%を超えたら**“要調整”
- 実行:
- 原則は“新規資金”で修正(売却は最終手段)
- 積立の向き先を**基準より“足りない側”**に寄せる
- 売却が必要なケース(最終手段):
- リスク管理上どうしても整えたい
- NISA内で税コストがかからない・取引コストが極小
例:米国が**+8%**オーバー → 次の数か月の買付を米国以外へ。5%未満まで戻れば通常運転。
3. AIの“乖離検知”プロンプト(コピペOK)
3-1 毎月の点検
あなたは長期インデックス運用の点検係です。
基準:全世界株式100%。ゆらぎ許容:米国・国内ともに基準比±5%。
入力:今月の私の実配分(例:全世界 100%、その内訳:米国 65%、国内 8%、先進国その他 20%、新興国 7%)。
出力:
①各カテゴリの乖離(%)を算出(基準=全世界内の比率をユーザーが貼る/または空欄なら「全世界100%基準」扱い)
②±5%を超えた部分に“注意”を付ける
③次の新規買付配分案(売却なし前提、○か月で自然復帰を狙う)
④行動メモ(次回点検日、月次ToDoを3つ)
注意:売却は最終手段。新規資金での調整を優先。
3-2 年1回の総点検(リバランス判定)
年次点検です。基準=全世界100%、許容ゆらぎ=±5%。
入力:今年の平均買付額、評価額、最終配分(米国/国内/その他)。
出力:
①±5%超の乖離があるか
②新規資金で戻す場合の目安額(○万円×○ヶ月)
③それでも戻らない場合の“最小限の売却案”(税/手数料の注意を添える)
④来年の積立配分の初期設定案(足りない側をやや多め)
3-3 ノイズ遮断(短期ニュース対策)
目的:短期ニュースで配分をいじらない。
出力:①ニュースの閲覧制限ルール(例:1日5分)②代替行動(運動/読書)③解除条件。
4. 実行のしかた(売らずに直す→必要なら最小限)
- 月次点検:AIで乖離を数値化(±5%を超えたら“要調整”)
- 新規資金で方向づけ:
- 積立先を足りない側に寄せる(例:米国オーバーなら米国“以外”に)
- 目標は数か月で5%以内へ自然復帰
- 年1回の総点検:それでも戻らなければ最小限の売却を検討(NISA内なら税はかからないが、売買の回転は増やさない)
- ログを残す:
- 「なぜ調整したか」を1行メモ
- 翌年は最初の積立配分を“足りない側”へ少し寄せて再スタート
重要:完璧に合わせる必要はない。±5%の“ゆらぎ枠”を上手に使うほど、手間もストレスも減ります。
5. よくあるQ&A(初心者向け)
Q. そもそも“基準の内訳”って?
A. オールカントリーは時価総額加重で世界の時価総額の比率を反映。米国が相対的に大きく、日本はその一部。ファンドの月次レポートに地域比率が出ています。そこを“基準”として扱いましょう。
Q. ±5%は絶対?
A. 目安です。取引コスト・労力・税の観点で、±5%(または±10%)のコリドーから始めるのが無理なく続きます。
Q. 国内比率は上げたくなる…
A. ホームバイアスは自然な感情。ただし集中しすぎはリスク。±5%内に収めるくらいの“ゆらぎ”なら、モチベーション維持にも役立ちます。
7. まとめ(ルール×AI=継続)
- 基準は全世界100%で、±5%のゆらぎは許容。
- AIが数値化→人は方針どおりに動くだけ。
- 売買を増やさず、新規資金の向き先でやさしく戻す。これが続く秘訣です。
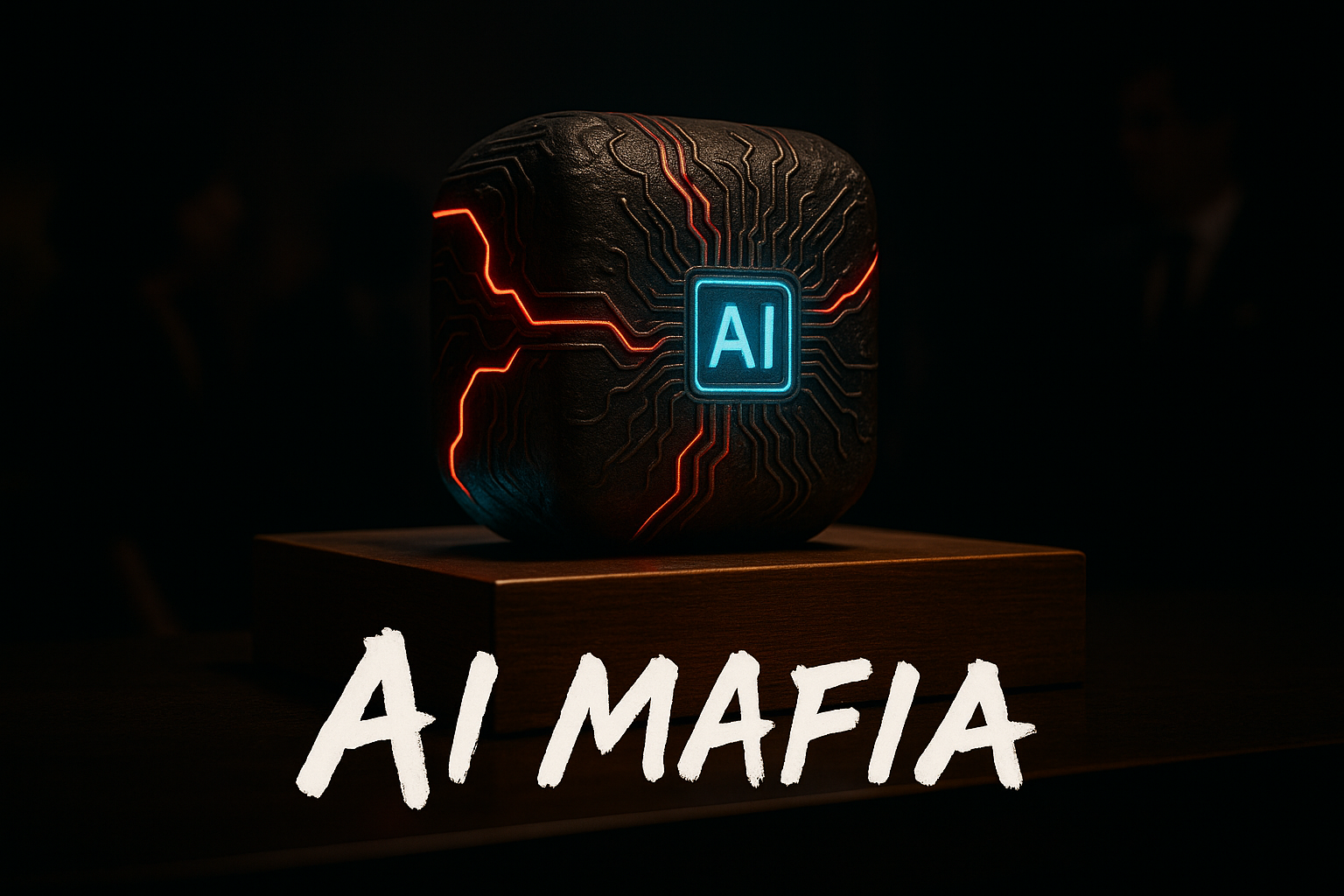

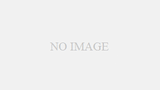
コメント