リード(結論)
- まずいくら必要かを決め、そこから逆算します。
- AIに「目標額・期限・想定利回り・ボーナス増額」を渡し、月額・年額・不足時の上乗せまで台本化。
- 投資は**新NISA×インデックス×ドルコスト(毎月自動)**が基本。感情で止めず、仕組みで続けるだけ。
1. 目標額の決め方(“金額×期限×使い道”で固定)
まず、教育費を3つに分けて試算します(数字は家計・ライフプランに合わせて調整)。
- 短期(0〜6年):保育・習いごと・学童など
- 中期(6〜18年):小中高での学費・塾・部活・留学など
- 長期(18〜22年):進学費用(入学金、授業料、生活費)
例:長期パート(大学相当)で目標1,000万円を22歳時点で準備、中期パートは毎年の家計から捻出など。
ここで**“教育資金ファンド(長期部分)”と“年間教育費(短中期)”を分けて**考えると台本が作りやすくなります。
AIへの入力テンプレ(目標額の逆算)
あなたは家計×投資の“教育資金コーチ”です。
目的:子どもの大学入学時(22年後)に【1,000万円】を確保。
前提:新NISAのつみたて投資枠でインデックスに毎月積立。想定利回りは【年◯%】(長期の保守目線)。
制約:途中で止めない/売買回転を増やさない。
出力:
1) 目標達成に必要な【月額】と【年間】積立額(賞与増額案も)
2) 不足が想定される場合の“段階的な増額テーブル”(初期→5年後→10年後)
3) ボーナス月の一時金の“向き先”案(不足側を優先)
4) 1行の台本(例:「毎月◯円+賞与で◯円、5年ごとに◯円増額」)
2. インデックスの選び方(“世界に丸ごと”+低コスト)
基本は、全世界株式インデックス(オールカントリー型)を軸に、
- 信託報酬:低コスト(年0.1〜0.2%台の目安)
- つみたて対応:新NISAの積立設定がしやすい
- 純資産:右肩上がりで継続性を確認
保守的にしたいとき
- 株式100%が不安なら、株式80%+債券20%などに分けて価格変動を緩和。
- ただしシンプルさは継続の味方。まずは1〜2カテゴリに絞って自動化を優先。
AIへの入力テンプレ(商品候補の棚卸し)
条件:全世界株式インデックスを基本。低コスト・つみたて可・純資産増。
補助案:株式80%+債券20%にした場合の月額差と、想定ボラティリティの比較(概念でOK)。
出力:商品“カテゴリ”の候補リストと、選定チェックリスト(手数料・積立可否・純資産推移)。
注意:具体商品名は例示のみに留め、最終決定はユーザー自身。
3. 不足時の上乗せ手順(“段階的に増やす”を台本化)
月額が足りない/途中で家計余力が出るときは、先に上乗せルールを決めておきます。
3-1 月収UP/固定費削減があったとき
- 超過分の70%を教育資金の月次積立へ上乗せ(残りは目的別・自己投資へ)
- 例:手取り+10,000円 → +7,000円を“教育資金ファンド”に増額
3-2 ボーナス月(年2回想定)
- 一時金の**50%**を教育資金ファンドへ
- ±5%の乖離ルールに沿って、“足りない側”へ向き先を寄せる(売却は最終手段)
3-3 不足が“大きい”場合(キャッチアップ台本)
- 5年刻みで段階増額(例:5年後に+3,000円、10年後にさらに+3,000円)
- 賞与の“固定割合”(例:毎回10〜20%)を教育資金へ
- それでも不足なら目標の“再設計”(金額・期限・学費配分の見直し)
AIへの入力テンプレ(上乗せ提案)
前提:目標1,000万円/22年後。現行の月額は【30,000円】、賞与は年2回。
今後5年間で家計余剰の平均が【+5,000円/月】見込める。
出力:
1) 段階的な増額テーブル(今→5年後→10年後)
2) ボーナスからの固定割合(10〜20%)を教育資金へ回す案
3) 乖離(±5%)に応じた“向き先”指示(売却なし前提)
4) 1行のキャッチアップ台本
4. 月次・年次の“台本”まとめ(チェックだけで回す)
月次(5〜10分)
- 積立実行の確認
- 家計余剰があれば上乗せ判定(AIに金額算出を依頼)
- 乖離は年次まで原則放置(±5%を超えたら“向き先”で整える)
年次(30〜60分)
- 評価額と配分をAIに一覧化
- ±5%超ならキャッチアップ手順を更新
- 翌年の初期積立配分を決め、次回点検日を登録
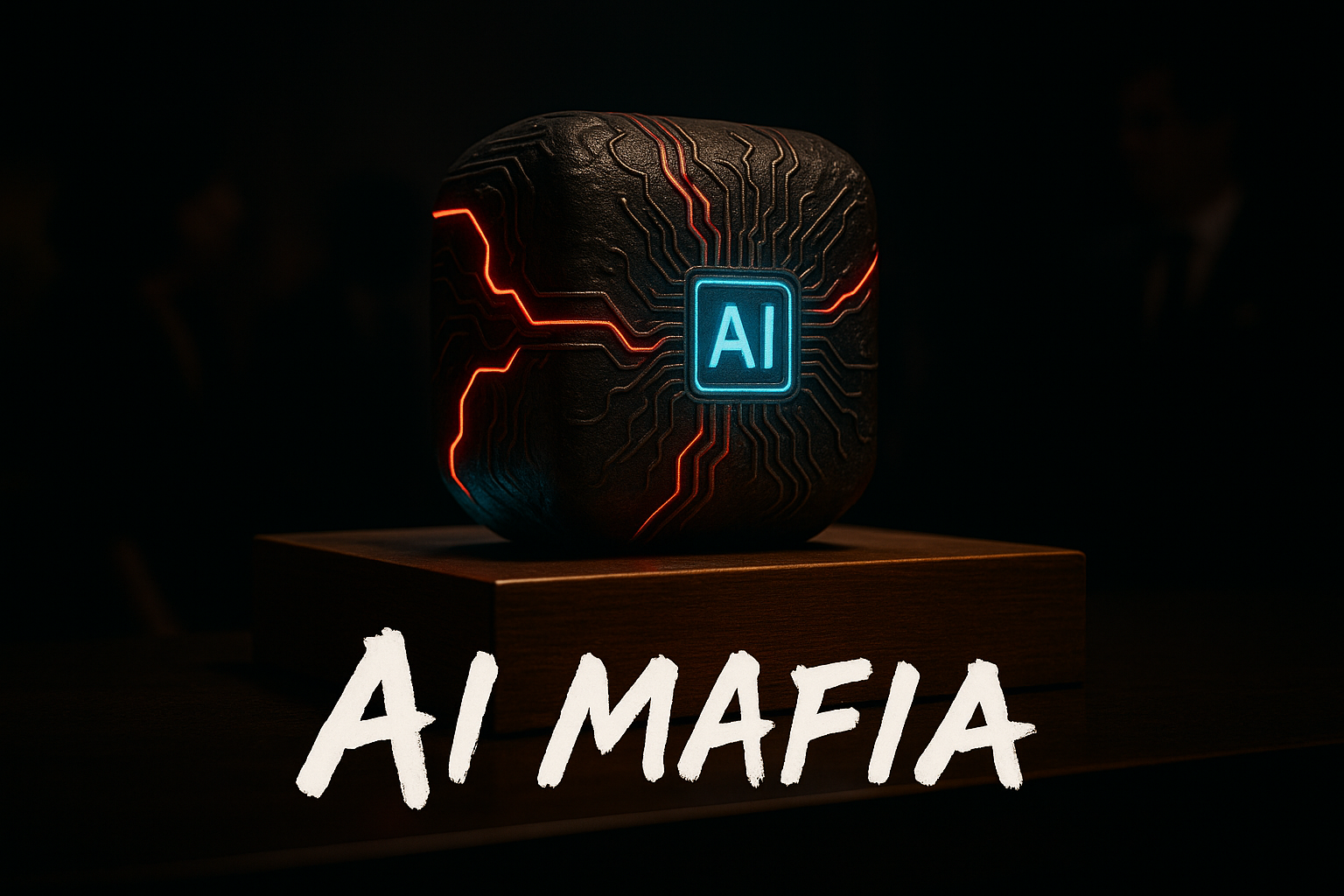

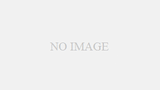
コメント