はじめに
メール、見積書、SNS、ブログ…「書く作業」は毎日の生産性を左右します。TextCortexは、ブラウザ拡張とチャット型アシスタント(ZenoChat)を中心に、今いる画面のまま下書き・推敲・要約・翻訳まで完結させるツールです。本記事では、機能と使いどころ、導入の流れを“実務視点”で紹介します。
サービスの全体像
- 形態:Webアプリ+ブラウザ拡張(Chrome/Edge/Brave など)
- コア機能:文章生成、リライト/要約、トーン調整、チャット回答、ナレッジ(知識ベース)連携、ペルソナ設定
- 想定ユーザー:個人事業主、スモールチーム、ブロガー/ライター、広報・サポート担当
主な機能
- ブラウザ拡張で“その場”生成
Gmail、Googleドキュメント、Notion、WordPress、各種フォーム入力欄などで、ポップアップから生成・推敲が可能。コピペ往復を減らします。 - ZenoChat(チャット型アシスタント)
通常のQAに加え、URLやPDFを読み込ませた知識ベースで“自社情報に即した回答”を出しやすくなります。 - ペルソナ/トーン設定
「広報担当」「CS対応」「カジュアル」「ややフォーマル」など、役割や口調をプリセット化。文章の“ブレ”を抑えます。 - リライト・要約・整形
文法の乱れや冗長表現を整え、ボリュームの増減、敬体/常体の切り替え、箇条書き化などをワンクリックで。 - 多言語対応
英日を含む多言語での生成・翻訳・パラフレーズに対応。海外サービスへの問い合わせや多言語SNS運用に有用です。 - テンプレート活用
メール返信、ブログ導入文、製品説明、SNSキャプションなど、よく使う型をテンプレート化して再利用できます。
使いどころ(ユースケース)
- メール対応の標準化
返信の骨子(結論→要点→次アクション)をテンプレ化し、文面はAIで整形。担当者によるムラを軽減。 - ブログ・記事制作
見出し構成→導入文→本文の草案→要約の順に支援。下書き段階でスピードを出し、仕上げは人が最終チェック。 - カスタマーサポート
よくある質問やナレッジを読み込ませ、一次対応の文案やサジェストを高速化。正式返信は必ず人が承認。 - EC・商品説明
要点整理→差別化ポイント→購入前の不安解消の順で説明文を生成。タイトル/説明のABパターンも容易。 - 社内資料の圧縮
会議メモや議事録を“結論→要点→補足”で再構成し、読みやすく配信。
はじめ方(最短ステップ)
- アカウント作成
公式サイトで登録(無料枠あり)。 - ブラウザ拡張を追加
GmailやDocs、Notion、WordPressでポップアップが出るかを確認。 - ZenoChatにナレッジを登録(任意)
自社サイトURLや公開ドキュメント、注意事項などを投入。 - ペルソナを作る(任意)
「広報・丁寧」「カジュアル」「事務・簡潔」など役割ごとに作成。 - 小さく試す
まずは「メール返信」と「ブログ導入文」だけAIに任せ、効果を測定。
実務でのコツ
- “骨子→整形”の順番にする
先に人が箇条書きで要点を書き、整形・肉付けをAIに任せると、的外れを減らせます。 - 禁止事項・NG例を先に伝える
自社で避けたい表現や必須ガイドラインをプロンプトに含めると、修正回数が減ります。 - テンプレを育てる
使って良かった指示文(プロンプト)をテンプレ化し、チームで共有。 - “要約→原文比較”で精度を担保
長文の要約は、要点が落ちていないかを必ず原文と突き合わせ。
注意点・限界
- 固有名詞/最新情報の正確性:公開前の事実確認は人が必須。
- 機密情報の扱い:取り扱い方針を明文化し、機密度の高い原文は取り込まない運用から始める。
- 使いすぎによる画一化:最終仕上げで“自社らしさ”を足す一手間が大切。
よくある質問(FAQ)
Q1. 日本語の自然さは?
A. 日常業務に支障のない品質です。重要文面(契約・プレス等)は人の最終確認を前提にしましょう。
Q2. 導入のハードルは高い?
A. ブラウザ拡張を追加すれば、既存の作業画面でそのまま使えます。ツール切り替えやコピペが減る点が利点です。
Q3. 最初はどの作業から?
A. 効果を実感しやすいのは「メール返信」「ブログの導入文」「社内資料の要約」。1週間だけでも作業ログを取り、削減時間を可視化すると判断しやすくなります。
まとめ
- 今いる画面のまま下書き・推敲・要約ができるのがTextCortexの魅力。
- ナレッジ連携×ペルソナで“自社の言葉”に寄せやすく、文章のブレを抑制。
- 小さく導入し、テンプレと運用ルールを整えることで、日々の“書くコスト”が目に見えて下がります。
付録:プロンプト例(コピペ可)
- メール返信(ややフォーマル)
「以下の要点に沿って、結論→要点3つ→次アクションの順で返信文を作成。敬語は過度に硬くしない。
— 要点:納期○日、見積○円の範囲、追加要件あり。」 - ブログ導入文(300〜400字)
「読者の悩み→放置リスク→本記事の解決策→得られること、の順で。専門用語はかみ砕き、短文中心で読みやすく。」 - 社内資料の要約
「下記の原文を、役員向けに“結論→意思決定ポイント→補足”で箇条書き化。冗長表現は削除。」
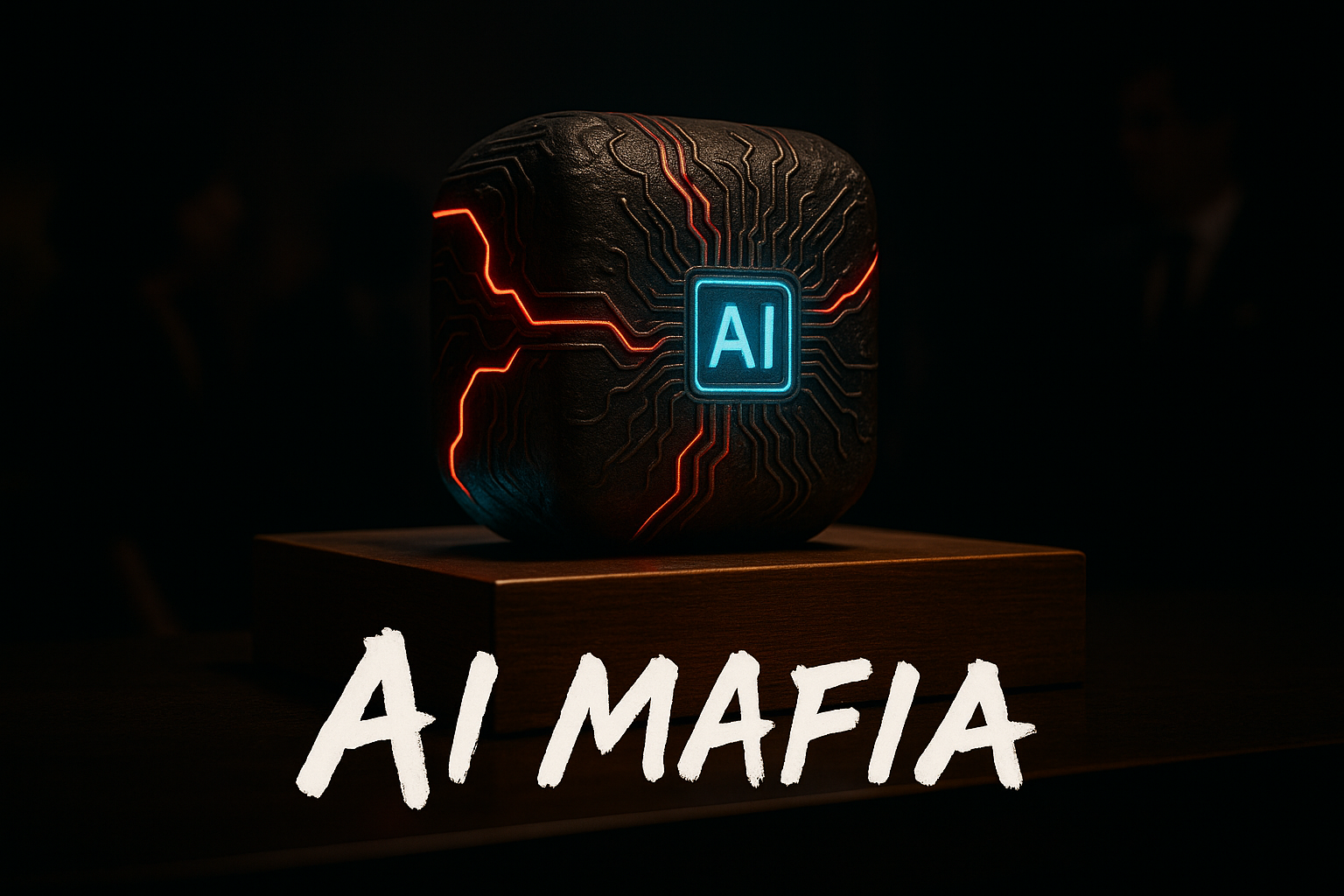

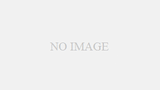
コメント